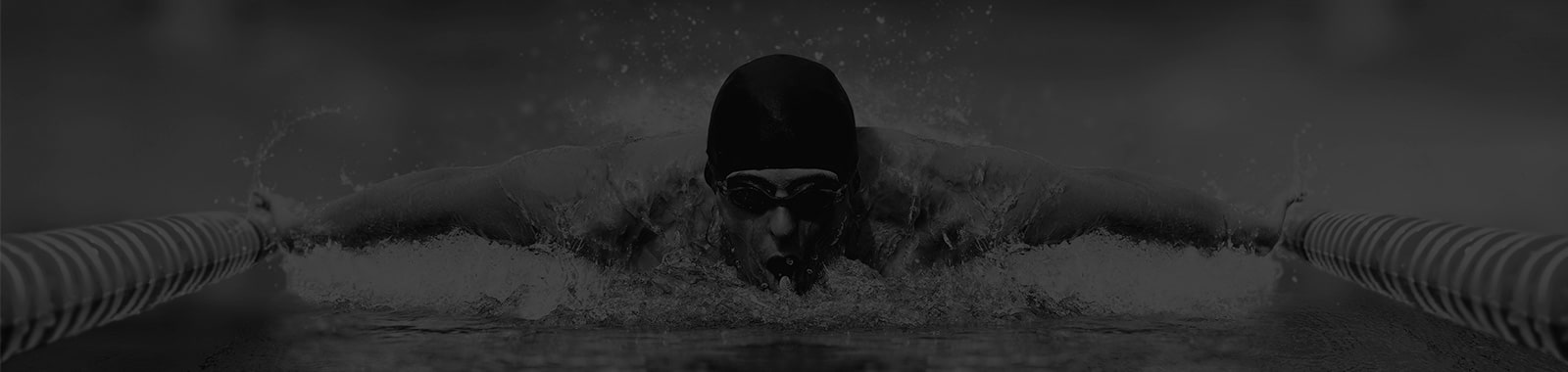運動やスポーツに 伴う痛み(4)
第14回「打撲・捻挫」
2024/09/30
“運動やスポーツに伴う痛み”に着目し、そのメカニズムやケア、対処方法などについて、症状ごとにスポーツドクターのお話をお聞きしています。今回も前回の「腱鞘炎」に続き、数多くのアスリートの治療を行ってきた土屋敢先生に「打撲・捻挫」についてお話を伺います。
打撲したらとにかく圧迫して血腫を散らす
Q1.前回の「腱炎・腱鞘炎」を慢性期の炎症とすると、今回お話を伺う「打撲・捻挫」は急性期の症状といえるかと思います。運動やスポーツに起因する「打撲」の原因やメカニズムを教えてください。
A1.サッカーやラグビーなどでは、相手選手の膝などが太ももに強く当たると激しい痛みが生じます。これを私たちは通称「ももかん」と言っています。正式には「大腿部打撲」、あるいは「大腿筋挫傷」の場合もあります。つまり打撲は、「直達外力(打撃や衝突など外力により加わった力が直接患部に達し作用すること)」によって主に筋肉から出血して発症するものです。 「ももかん」の場合、大腿骨が太ももの真ん中にあることで、筋肉が大腿骨にぶつかってロックされ、その衝撃で損傷し出血するというのが典型的なケースです。その後にできる血の塊を血腫といいますが、血腫は大腿骨のすぐ上にできます。肉離れが比較的表層で起きるのに比べ、「ももかん」の打撲の血腫はかなり深いところで起こります。
Q2.「打撲」が起こりやすい運動や競技にはどのようなものがありますか。
A2.サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツです。サッカーでよく「削る」という言葉を聞くと思います。相手選手にぶつかる際に意図的に激しく当たり、ときにはケガをさせてしまうことです。柔道でも多くみられ、大きな血腫をつくることがあります。

Q3.打撲」は相手によって引き起こされる場合が多いと思いますが、なるべく程度を軽くするような方法はありますか。
A3.残念ながらありません。お互いにフェアプレーの精神で、クリーンなプレーをするしかないでしょう。相手がいることですし、不可抗力の場合もあります。できる対策として挙げるなら、判断力のスピードを上げることぐらいでしょうか。判断が一瞬でも早ければ、相手と接触しないで済むかもしれません。 例えばサッカーですと、相手よりも早く前に出てボールをさばければケガは防げるかもしれません。それが出遅れたことで、相手とより近い距離で対峙しなければならなくなる。とにかく「一歩でも早く出るためにはどうすればよいか?」を日ごろから常にイメージすることが大切でしょう。とはいえ、どうしてもディフェンスやフォワードの選手は競り合いになってしまいます。まして柔道は一対一ですので、程度を軽くするということは難しいです。
Q4.では「打撲」してしまった場合の対処方法(セルフケア)を教えてください。また治療機関に行ったほうがよいなどの判断の仕方なども教えてください。
A4.とにかく圧迫することです。冷やす以前に圧迫です。外傷を受けたときに必要な「RICE処置」という応急処置の方法があります。 Rest(安静)/ Icing(冷却) / Compression(圧迫) / Elevation(挙上)の4つの処置の頭文字から名付けられたものです。早急に行えば、内出血や腫れ・痛みを抑えて回復を助ける効果があるとされています。ただこれは処置の順番というわけではなく、打撲の場合はまずCompression(圧迫)です。要するに、打撲すると血の塊ができてしまうので、血腫を散らすことが目的です。血の塊は3~4週間経つと、骨化性筋炎、あるいは異所性骨化といって、血腫の一部が骨化してしまうことがあります。こうなると治りにくくなるケースもあります。それを防ぐために、テーピングや包帯で打撲した部分を圧迫し、全部平たく散らすようにして、その上から冷やすことです。 現場での適切な応急措置は重要ですが、ごく軽い打撲は別にしてやはり早期回復のためにはすぐに治療機関に行くことをお勧めします。
| Compression(圧迫) | Elevation(挙上) |
|---|---|
| Icing(冷却) | Rest(安静) |
子どもの捻挫は剥離骨折かも、医療機関を受診すること
Q5.次に、運動やスポーツに起因する「捻挫」の原因やメカニズムを教えてください。
A5.捻挫(ねんざ)とは、不自然な形にひねりくじくことで関節に強い力がかかり、靱帯や腱、軟骨などが傷つくケガのことです。関節部分の血管が傷ついて内出血を起こすとその部分が腫れてきます。 捻挫は圧倒的に足関節の損傷が多いです。前回もお話ししたとおり、膝は主に屈曲・伸展の2方向の動きですが、足首はそれに加えて回旋があります。可動性が広いので、内側にひねって生じる内返し(内反捻挫)と外返し(外反捻挫)の大きく2種類に分けられます。 靱帯とは、関節の骨の先端部に付着している線維性の結合組織のことです。役割としては、骨同士をつなぎ、関節の動きを容易にしたり制限したりしています。捻挫は基本的にはこの靱帯の損傷です。足関節の場合、ほとんどが保存療法で手術にはならないのですが、靱帯は完全な治癒が難しいので少し緩くなってしまうケースが多くあります。
Q6.「捻挫」が起こりやすい運動や競技にはどのようなものがありますか。
A6.予想できない動きが多い競技、つまりサッカーやバスケットボールなどでは非常に起きやすいです。捻挫しやすい条件というのは、ストップやターンの動きや切り返しの動作、ジャンプからの着地、また接触プレーなどの場面で多発します。かつ体育館のようなピッチの硬い場所でも起こりやすいです。グラウンドの場合少し滑るくらいであれば、打撲はしてもひどい捻挫にはならないでしょう。 ただ人工芝だと下がアスファルトやコンクリートなので、硬くて地面にロックされてしまうのです。そのため、最近は女子サッカー選手の捻挫が増えています。

Q7.「捻挫」の予防方法は何かありますか。
A7.もちろん最低限の筋力は必要ですが、小学校や中学校のときに、いかにバランスの訓練をしているかです。特に小学生時代が大切です。関節が硬いとケガをしやすいので、柔軟性と可動域の広さを獲得しておくように心がけることが大切です。 そして、体幹や股関節がぶれるとひねりやすくなります。そのために基本的な筋力及び体幹や股関節を軸としたバランストレーニングを最優先に行いましょう。 他にも、各競技特性に合わせた動作のチェックをすることが予防につながるでしょう。特に小学生への指導者にお伝えしたいのですが、小学生の捻挫に限ると、足関節ではなく、外くるぶしの腓骨の遠位の剥離骨折がほとんどです。ですから、子どもの捻挫の場合は医療機関を受診してください。数日で良くなるので見逃されがちですが、剥離骨折の場合足首が不安定なままですから後々、手術の必要が出てくるケースも多々あります。
Q8.「捻挫」の対処方法(セルフケア)を教えてください。また治療機関に行ったほうがよいなどの判断の仕方なども教えてください。
A8.やはりその場での対処で優先すべきは、「とにかく圧迫してください」ということです。冷やすよりも、まずテーピングや包帯による圧迫です。これで後々の治療のスケジューリングも変わり、勝負が決まるといっても過言ではありません。その後にできるだけ動かさないようにして冷却という流れになります。 歩けないほどの歩行時痛がある場合は必ず受診する。さらに重ねて言いますが、小学生は剥離骨折のケースが考えられるので、同じく必ず受診してください。

-
今回の先生
北千葉整形外科 幕張クリニック
スポーツ医学・関節外科センター長
土屋 敢さん
経歴
1970年生まれ。長野県出身。 千葉県立千葉高校卒業。 千葉大学医学部卒業。 千葉大学整形外科入局。 千葉大学医学部整形外科大学院卒業。
2003年~2013年3月まで、川鉄千葉病院(現・千葉メディカルセンター)スポーツ整形外科部長。 2013年4月より現職。
専門は膝・足関節外科、スポーツ整形外科。
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会スポーツ医専門医
脊椎脊髄病医専門医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
千葉県サッカー協会スポーツ医学委員会委員長/理事
サッカー関連の業務は多く、2006年には第15回アジア大会サッカー男子日本代表チームドクターや北京オリンピックサッカー男子日本代表チームドクター等を務める。