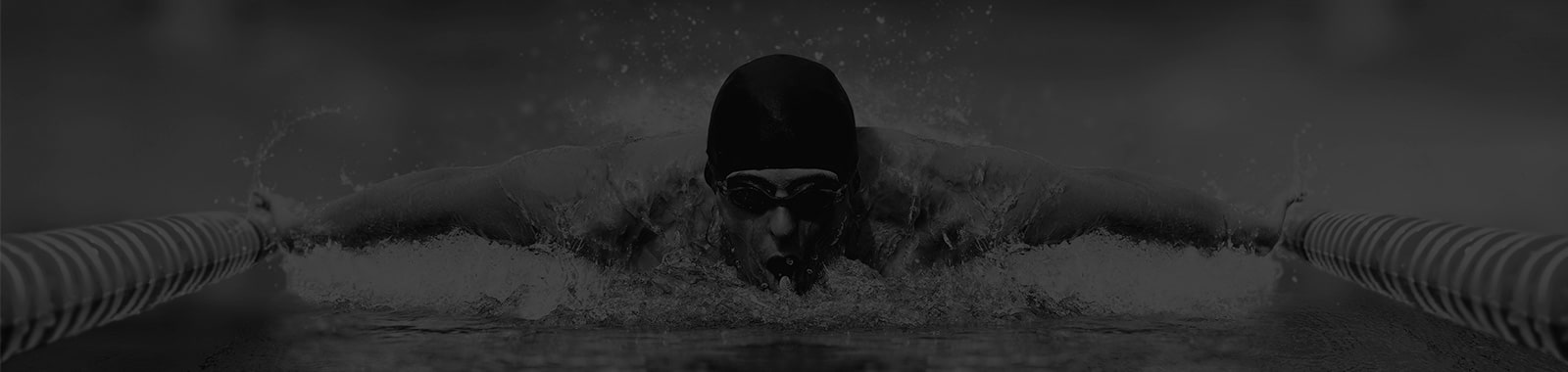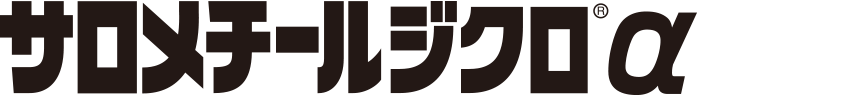日常生活に取り入れやすいトレーニング
第8回「日常のトレーニングを前提とした中長期目標」
2022/09/02
前回は、「毎日簡単に行えるトレーニング」と題してアスレティックトレーナーの栗田英行さんにお話をお聞きしました。今回は、引き続き栗田さんに日常のトレーニングを前提として、より長いスパンを見据えてトレーニング行う場合の中長期計画について、様々な観点からお話を伺いました。
どの大会にピークを持ってくるのかが大切
Q1.日常のトレーニングを前提として、月単位や年単位でのトレーニング計画の立て方のポイントについてお聞かせください。
A1.毎試合、毎大会でベストパフォーマンスを発揮するというのは難しいことです。年間のトレーニング計画をたてる時は、年間スケジュールのうち、どの試合や大会にピークを持ってくるのかを明確にし、そこに照準を合わせて計画を組むのが良いでしょう。競技によって差異はありますが、ベストパフォーマンスは年間2回程度が限界と考えています。ですから、大事な2試合程度をピックアップし、そこに向けて計画を組むことが重要です。
例えば、水泳の場合、技術力、持久力とスピードなどの強化が必要です。試合までのトレーニング期間をそれぞれにどの程度振り分けるのかを決めて、目的別に分けて練習するのがいいでしょう。また年間を通して試合があるような競技では、十分な強化期間を作るのが難しい場合があります。そのため、シーズン中は強化というよりは筋力や体力の維持がトレーニングの目的となるでしょう。
スポーツ愛好者の方も同様に目標とする試合や大会に照準を絞り、そこに向けてトレーニング計画を組むのが良いでしょう。年間計画の立て方の例としては、半年に1回大事な試合や大会があるなら、半年間のスケジュールとして、最初の2ヶ月は全般的な体力の強化、次の2ヶ月は弱点の克服、最後の2ヶ月は実戦を想定した練習を中心に行なう、などが考えられます。それぞれの課題の数や内容は違いますので、区分けはそれぞれで変更してください。
トレーニング内容に関しては、一定期間続けてくことをおすすめします。トレーニングの効果が現れるにはある程度の時間が必要です。毎回トレーニング内容を変えてしまうと、トレーニング効果が出にくいので、どんなトレーニングを行うのかしっかり決めた上で取り組み始めることをおすすめします。

Q2.次に、中長期計画に関して、個別のケースの対応についてお伺いします。慢性的な筋肉痛や筋肉疲労を抱えているアスリートにとって、有効な中長期のトレーニングについて教えてください。
A2.慢性的な筋肉痛がある場合は、なぜそこに痛みが発生するのか原因を明確にする必要があります。試合や練習量が多すぎてオーバートレーニングが原因のケースもありますし、体重減少が原因で慢性疲労を抱えているケースもあります。その場合は、当初の月単位や年間のトレーニング計画を見直し、試合数、練習量を調整したり、適正体重に戻すなどの対処をしてください。女性アスリートだと、貧血が原因の場合があります。その際は鉄分摂取や食事の改善などでアプローチします。
また、うまく使えていない筋肉が原因となっている場合もあります。それは動作に癖があり、1カ所に負荷がかかりすぎて慢性的な筋肉痛が発生している可能性があります。この場合、筋肉痛の部分はストレッチやケア等で対応しますが、原因である使えていない筋肉を鍛えなければ根本的に改善しませんので、ストレッチ、ケアと同時に使えていない筋肉をトレーニングすることも併せて行い、対応します。 使えていない筋肉を鍛える場合はできるだけシンプルなトレーニングが望ましく、筋肉がうまく使えるようになったら、全身のトレーニングに移り、その後、競技動作へ繋げていくといった流れで行います。
スポーツ愛好家の方が、ご自分の使えていない筋肉を発見するのは大変難しいです。慢性的な筋肉痛を抱えている方は、スポーツトレーナーなどの専門家に是非相談してください。

Q3.トレーニング計画を立てる際には、青少年から、中・高年までの世代別でどんなことに気をつけるとよいでしょうか。
A3.各年齢の発達の過程を理解したうえで立ててほしいですね。青少年の場合は筋肉を大きくするウエイトトレーニングではなく、神経系の発達を促すことを目的とすると良いでしょう。例えば、縄跳びをする際に片足で行ったり、前進や後進しながら行ったりすることで、全身のバランス能力を向上させることが出来ます。あるいはキャッチボールを利き腕ではない方で行うことも、神経系を発達させる良いトレーニングです。
複数の競技に取り組むマルチスポーツもいいですね。多くのトップアスリートが中学生までにマルチスポーツを経験しています。複数のスポーツを経験する事によって、自らの特性や趣向を把握し、その後に行うスポーツを絞っていくことができます。
高校生くらいになると、骨格筋が発達してきます。それでもいきなり重いウエトトレーニングではなくて、まずは各ウエイトトレーニングの正しいフォームを身につける事が大切です。正しいフォームを身につければ、その後ウエイトトレーニングの負荷を上げても怪我に繋がりません。
最近「腰椎分離症です」と来院する高校生が多いと感じます。分離症は骨格が出来上がっていない成長期に発症することがほとんどです。小中学生時代に練習量が多すぎたり、腰に負担がかかる動作が多かった事が原因の可能性があります。高校生になるとある程度骨の成長が止まり、骨格が完成します。それまでに腰の不調を見落とすことなく、腰に負担がかかる動作を改善しておきたいですね。高校生になって「痛みがあって思うように動けません」ということになりかねず、本当にもったいない事です。
中高年の場合は、疲労の回復が遅くなっていますので、トレーニング頻度や強度を調整して無理なく余裕のある計画を立てて行うのがいいでしょう。トレーニング計画以外にも、睡眠時間や食事、酒量などにも気をつけて日常生活を送り、体調維持に努めるようにしてください。
高校生や中高年のトレーニング計画を立てる際にも専門的な知識が必要となってきますので、私たちトレーナーがプロフェッショナルとしてお役に立てる時代がくるといいなと思います。

筋肉の発達に大切なのは、運動・栄養・休養
Q4.女性アスリートや女性スポーツ愛好者で、妊娠されている方などは妊娠期間中、産後等で中長期目標を立てる際に気をつける事はありますか?
A4.現在は妊婦の方も適度な運動が推奨されています。軽めの有酸素運動、ヨガ、マタニティヨガなどが良いと思います。ただ各個人で状況は異なりますので、必ず主治医へ「運動をしてもよいかどうか」を相談、確認していただくことが大切です。
また出産までではなく、出産後の身体の回復を目的としたトレーニングまで計画しておくと良いのではないでしょうか。
詳細については、日本臨床スポーツ医学会のサイトに「妊婦スポーツの安全管理基準」が示されていますので、ぜひ参考になさってください。
https://www.rinspo.jp/files/proposal_28-1-01.pdf
日本でも、結婚、出産を経て、復帰、活躍する女性のトップアスリートが現れてきました。以前に比べて選手寿命が延びたのと同時に、競技を続けやすい環境が整いつつありますね。一般のスポーツ愛好家も正しい情報に基づいて長く競技を続けて欲しいと思います。
メンタルのリフレッシュも必要
Q5.身体の健康維持・増進と併せて、中長期ではメンタル面のトレーニングも必要になってくると思いますが、効果的なトレーニング方法があればお聞かせください。
A5.長期でトレーニング計画を立てて行っていく場合に、計画通りに進まなかったり、前向きになれない時期というのはあるものです。そんな場合は、「メンタルが弱いからだ」ととらえるのではなく、メンタルのリフレッシュを図るのが良いでしょう。長期の休養は、私は身体面よりもメンタル面で必要なことだと考えています。日ごろから努力し続けストイックに取り組んでいるアスリートにとって、「リフレッシュできる時間」は重要です。そして「次に向けてもう一度トレーニングを始めたい!」とモチベーションが上がるような、自分ならではのリフレッシュ法を見つけるのが良いでしょう。「美味しいものを食べる」でも、「映画やコンサートなどエンターテイメントを楽しむ」でも構いません。メンタルのリフレッシュをしていけば身体のほうも自ずと休まるはずです。

Q6.中長期計画においても、医薬品の活用が重要と思われます。筋肉や各部位などの持続する痛みへの対応や抑制等について、サロメチールの活用や効用についてお聞かせください。
A6.赤いサロメチールはスポーツ前後のケアだけでなく、休養時や夜寝ている間にも塗ると血行を促進させてリカバリーにつながるでしょう。 またサロメチールジクロシリーズは、ジクロフェナクナトリウムが配合され、痛みに対しての効果が高いので「今日は痛みが強いな」という場合は、サロメチールジクロシリーズのローションやゲルを痛みの部位や状況に合わせて使うと良いでしょう。 睡眠時間を有効活用すれば、夜塗って、寝ている間にリカバリーや痛みの除去が可能です。テープ剤の「サロメチールジクロα・サロメチールジクロLα」もあるので、そちらも活用されると良いと思います。

この記事で紹介された製品
今回の先生
FIET Conditioning
代表栗田 英行さん経歴
1969年1月28日生まれ。静岡県出身。鍼灸マッサージ師の資格取得後、㈱ピープル(現コナミスポーツ)に入社。同社接骨院に勤務しながら競泳を中心としたトレーナー活動を行う。2008年北京オリンピック・競泳チームのトレーナーとしてチームに帯同。2009年に日本スポーツ振興センターに移り、国立スポーツ科学センター(JISS)で、フェンシング、トライアスロン、バドミントン等の日本代表選手のトレーナー活動に携わる。2017年からはフリーとして活動。2022年に埼玉県・さいたま市に「FIET Conditioning」を開業。スポーツ医学修士。